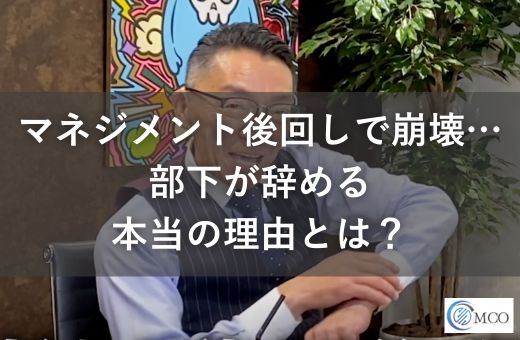
部下が辞める本当の理由は、あなたの「マネジメント後回し」かもしれない
「部下が続かないのは、若手の根性や能力のせいだ」と思い込んでいませんか?
実は、多くの退職理由はそこではありません。本当の原因は、上司であるあなた自身が「マネジメントを後回し」にしていること。つまり、部下のケアや育成に目を向ける余裕がないことが、静かに組織を壊していっているのです。
YouTubeでみたい人はこちら↓
忙しさに追われる管理職が、気づかぬうちにチームを壊している
ある企業の部長は、毎日の会議や取引先対応に追われ、部下との1on1を何度も断り続けていました。「今週はちょっと無理」と、予定を先送りしているうちに、いつの間にか誰も彼に相談しなくなり、最終的には退職者まで出てしまったのです。
この話、他人事ではありません。現場を動かすことに集中しすぎると、マネジメントが“ついで業務”になってしまう。その結果、部下との信頼関係が築けず、相談も成長も止まってしまうのです。
部下のミスは、「能力の問題」ではなく「教え方の設計ミス」
若手に資料を頼んだらミスが多く、自分で修正するハメに…。そんな経験、管理職なら一度はあるでしょう。「先週も同じことを教えたのに」と感じるたびに、「なんで覚えないんだ」とイライラしてしまう。
でも、実際にはチェック方法や見直し方を教えていなかったり、本人の性格や理解スピードを見極められていなかったりする場合がほとんどです。「見直した?」と一言声をかけるだけで変わる場面は、意外と多いものです。
部下が成長しないのではなく、上司が「どう育てるか」をまだ理解していないだけなのかもしれません。
パワハラを恐れすぎて、何も言えなくなっていないか
「ちゃんと確認して進めて」と少し強く伝えただけで、「怒鳴ってましたけど大丈夫ですか?」と別の社員に指摘された――。そんな状況に、戸惑う上司は少なくありません。
厳しく言えばパワハラ、何も言わなければ放置。こんな極端な二択の間で、マネジメントはどんどん萎縮していきます。しかし実際には、パワハラと指導の違いは「伝え方」よりも「伝わり方」にあります。
コミュニケーションに不安があるなら、まずは「どう伝わるか」を意識して、言葉の選び方や話し方を工夫する。それだけで、部下との関係はぐっと良くなることもあるのです。
「指示待ち部下」を育ててしまっているのは、誰か?
毎回「次はどうすればいいですか?」と聞かれる部下に対して、「またか…」と感じてしまうこともあるでしょう。でも本当にその部下は、自主性がない人なのでしょうか?
人は誰でも、「依存→自立→自走→支援」という4段階で成長していきます。今その部下が“依存”の段階にいるなら、すべきことは「突き放す」ことではなく、「どうすれば考えて動けるようになるか」を一緒に考えることです。
もし本人がそもそも自走を望んでいないなら、無理に求めても逆効果。まずは部下自身が「どうなりたいか」を聞くことが、マネジメントの第一歩です。
「年功序列で昇進」は、組織を腐らせる
年数が経ったからといって、人望のない部下を昇進させるべきか? これは多くの組織で直面するジレンマです。
本来、昇進はチームへの貢献や信頼があってこそ意味があります。「金属年数を満たせばOK」というルールがあるとすれば、それこそが仕組みの欠陥。ルールは組織をよくするためにあるのであって、形だけを守るためにあるのではありません。
現場が納得しない人事は、現場の士気を一気に下げます。
年上の部下に気を遣いすぎていないか?
40歳の上司に対し、部下は60歳。言い方を間違えると不機嫌になり、かといって遠慮しても言うことを聞かない…。こんな悩みを抱えている方もいるかもしれません。
でも大切なのは、年齢よりも日々の信頼関係です。年上であっても「同じチームの一員」であるという前提で、伝えるべきことはしっかり伝える。そのうえで、日々の会話では相手への敬意を忘れない。このバランス感覚が、年齢差を超えたマネジメントを可能にします。
まとめ:「できない部下」などいない。「放っておかれた部下」がいるだけ
マネジメントは「センス」や「カリスマ性」ではなく、技術です。
そして、やり方さえ知っていれば、誰でも身につけられる力です。
「忙しいから」「怒られるのが怖いから」とマネジメントを後回しにすれば、いつか部下は去っていきます。逆に、たった一言の声かけや、小さな工夫が、チームの未来を大きく変えるきっかけにもなります。
あなたのチームの課題は、「部下」の問題ではなく「上司である自分」の課題かもしれません。今こそ、マネジメントを学び直すときです。


