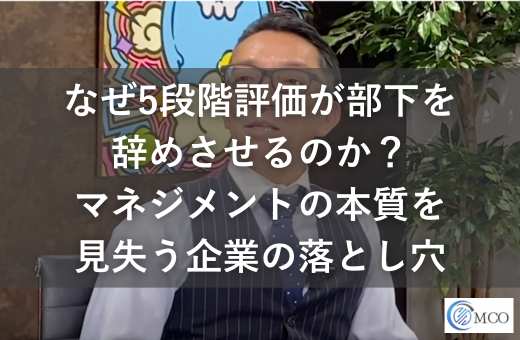
なぜ5段階評価が部下を辞めさせるのか?マネジメントの本質を見失う企業の落とし穴
「マネジメントって難しい」と感じていませんか?
その背景には、形式ばった評価制度や、“なんとなくの常識”が根強く存在しています。特に中小企業で使われがちな「5段階評価」は、その代表例。
本記事では、実際のセミナー対話をもとに、部下が辞める本当の理由と、マネジメントが崩壊する構造をわかりやすく紐解きます。
YouTubeで未来人はコチラ↓
評価に縛られる人は、成果より他人の目を見ている
動画冒頭で語られたのは、なぜ人は「評価」に敏感なのかという問い。
5段階評価の話題がバズった理由を「気になる人が多いから」と分析する登壇者に対して、もう一人はズバッとこう言い切ります。
「大した成果を出していないから、他人の評価ばかり気にする」
アドラー心理学では、他人の目を気にしすぎる人ほど、実は自己中心的であるとされます。
つまり、“他人にどう思われるか”ばかりを気にする人ほど、自分自身と向き合っていない。これはマネジメント層にも当てはまる話です。
中小企業で5段階評価が失敗する理由
「評価制度は必要」という声は多くありますが、こと中小企業においては、その制度が機能不全に陥りやすいと指摘されました。
▽その主な理由は以下の通り
- 評価が3以下だとモチベーションが下がる人が多い(実際、全体の6割はやる気を失う)
- 評価1や2の人はほぼネガティブに捉える
- 「あなたは3です」と言われて喜ぶ人はいない
こうした仕組みでは、半数以上の社員が「残念な気持ち」になる制度になってしまいます。
「ノーレイティング」という新しい選択肢
5段階評価をやめて、「ノーレイティング(評価しない育成型マネジメント)」という手法も提案されました。
これは、社員一人ひとりのキャリアビジョンを起点に育成プログラムを設計する方法です。
ただしこれも「難しいから無理」と諦めてしまえば、現状維持すらできません。
制度を変えたいなら、マネジメント側が学び直す覚悟が必要です。
昇給が前提だった時代と、今は違う
評価制度はもともと「経済が右肩上がりの時代」に最適化されたものでした。
売上が伸び、評価が少しでも良ければ給料も上がる、という前提があったからこそ機能していたのです。
しかし今は違います。売上が伸びていない中で給与を上げれば、企業の利益は減ります。
この環境下で機能しない制度を続けることこそが、モチベーションと成果を損なう大きな要因なのです。
部下が辞めるのは「制度」ではなく「上司」のせい?
最後に語られたのは、マネジメントの本質に触れる鋭い一言。
「部下が成長しないのは、上司の責任です」
上司が忙しい、制度が古い、やり方が分からない——すべて“できない理由”に過ぎません。
逆に言えば、正しいやり方を学び、実行すれば、マネジメントはもっと楽に・うまくいくということでもあります。
まとめ:評価制度に頼らず、部下と向き合える上司になろう
本記事で紹介したのは、表面的なマネジメント論ではなく、「なぜ評価制度が人を苦しめるのか?」という根本に迫る内容です。
マネジメントが崩壊するのは、制度や部下のせいではありません。
本気で育てようとせず、正しくマネジメントしようとしない上司の在り方が原因なのです。


